ベルゼブブ――聞いたことはあるけれど、実際はどんな存在か知っていますか?
キリスト教やユダヤ教の悪魔の一人として有名ですが、実はもともと神だったと言われています。
サタンは元天使でそれはそれで大転落だなと思っていましたが、ベルゼブブはまさか……神⁉︎
と驚いてしまいますよね。
かくいうわたしも、ベルゼブブ=ハエの悪魔らしい、くらいしか知らなかったのですが、よくよく調べてみて驚きました!
この記事では、ベルゼブブの「神→悪魔」という波乱万丈の歴史をたどり、マンガに登場する姿まで紹介します。
ベルゼブブはもともと神だった
ベルゼブブ(Beelzebub)は、キリスト教やユダヤ教の悪魔の一人で、地獄の大公として知られています。
しかし、その起源をたどると、もともとは土着の神であり、悪そのものではありませんでした。
ベルゼブブはもともと「バアル・ゼブル(Baal Zebul)」という名前で、“高き所の主”という意味を持つ神様でした。
古代ペリシテという、地中海東部沿岸(現在のイスラエル南部~ガザ地区あたり)の民族の間で信仰されていました。
この民族は、聖書の中ではイスラエル人としばしば戦う存在として登場します。
ベルゼブブは豊穣と天候を司り、作物の実りをもたらす存在として崇拝されていました。
しかし、ユダヤ教が広がる過程で、神から悪魔へと転換される存在として扱われるようになりました。
偶像崇拝禁止がベルゼブブを悪魔にした理由
かつて地方の国や地域は、独立した文化を築いていました。
それぞれの土地の神様への信仰が強ければ強いほど、その土地の団結力も強まります。
つまり、宗教が強ければ、それだけ支配力も強まるということです。
そこに目をかけて世界を支配しようとしたのがユダヤ教です。
ユダヤ教は、“偶像崇拝の禁止”という手法を使って、地方の多神信仰を抑え、唯一神信仰を政治的・宗教的支配の道具として利用しました。
偶像崇拝とは?
偶像崇拝(Idolatry)とは、神そのものではなく、神をかたどった「形(像)」や「物」を崇めることを指します。
たとえば:
- 神様の像を作って拝む
- 太陽や星など自然物を神として崇める
- 人間や動物を神の化身として祭る
こういった行為が「偶像崇拝」です。
ベルゼブブが神として祀られていた地域も、農耕や狩猟など自然と密接に関わる文化を持っていました。
太陽や星、動物などを神聖視することは当然の流れでしたが、ユダヤ教ではこれらが“偶像崇拝”として否定されました。
結果として、ベルゼブブのような土着の神々は「敵対的存在」として位置づけられ、神から悪魔へと転じていったのです。
十戒と偶像崇拝
偶像崇拝は、モーセが神から授かった十戒の一つでもあります。
モーセの十戒については別の記事で詳しく解説しています。理解を深めたい方はこちらもどうぞ。
旧約・新約聖書におけるベルゼブブ
ベルゼブブは「ルシファー(サタン)に次ぐ2番目に強い悪魔」と言われることがあります。
しかし、聖書にはそのような記述はありません。
- 旧約聖書:ベルゼブブが神から悪魔に堕天したことが仄めかされる箇所はあるものの、明確には描かれていません。
- 新約聖書:ベルゼブブは悪魔界の幹部の一人として描かれ、サタンや他の悪魔たちとともに登場します。
ベルゼブブが「暴食の悪魔」になった理由
「暴食の象徴」「サタンに次ぐ二番目の悪魔」といった設定は、中世~ルネサンス期の神学者によるキャラ付けが起源です。
当時、神学者たちは聖書に書かれた罪や戒律を民衆にわかりやすく伝えるために、悪魔たちに役割や性格を与えて体系化しました。
ベルゼブブもその過程で「暴食の象徴」「堕落の元凶」「サタンの右腕」といったキャラクターとして定着したのです。
「ハエの王」の由来
ベルゼブブ(Beelzebub)の名の起源は、古代セム語の「バアル・ゼブル(Baal Zebul)」。
意味は「高き所の主(Lord of the High Place)」や「崇高なる主」です。
しかし、ユダヤ教側はこれを意図的にBaal Zebub(バアル・ゼブブ)=“ハエの主(Lord of the Flies)”と改変しました。
「ゼブル(Zebul)」=“高貴・崇高”を「ゼブブ(Zebub)」=“ハエ”に置き換え、敵対する神を侮辱したのです。
ハエが象徴する「誘惑・腐敗・疫病」
中世ヨーロッパでは、ハエは「誘惑」「腐敗」「疫病」「堕落」の象徴として扱われました。
悪魔の活動の比喩として頻繁に登場します。
たとえば:
- 悪魔が人の耳に囁く=ハエがまとわりつく誘惑
- 心の弱さに巣食う悪念=腐敗を好むハエ
- 疫病や不潔な環境=神の罰としての悪魔の仕業
このような文化的イメージが結びつき、「ハエの王」ベルゼブブ像が定着していきました。
文学におけるベルゼブブ(『蝿の王』)
現代文学では、ウィリアム・ゴールディングの小説
『蝿の王(Lord of the Flies)』が象徴的です。
文明を失った子供たちの中に芽生える暴力と堕落を描き、ベルゼブブの「腐敗」や「堕落」の象徴性を文学的に再利用しています。
腐敗と再生の象徴としてのベルゼブブ
「腐敗=悪」だけではありません。
自然界では腐敗は新しい生命の循環を支えるプロセスです。
死んだ生物が分解され、土となり、新しい生命を育む――これもまた秩序の一部。
宗教や神話でも、死と腐敗は再生や秩序の回復を意味することがあります。
ベルゼブブの「ハエの王」というイメージも、単なる悪や堕落ではなく、変化と再生の象徴として解釈することができます。
ベルゼブブが登場するマンガ紹介
『鬼灯の冷徹』
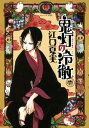
日本の地獄を舞台としたコメディマンガ。
ベルゼブブは外交先のエリートとして登場します。
サタンや奥さんに振り回される姿が魅力的で、地獄の官僚的な描写の中でもユーモアが光ります。
『聖☆おにいさん』
悪魔たちがどこか可愛らしく、繊細に描かれる中で、ベルゼブブもまた愛嬌のある存在として登場。
ルシファーをはじめとする悪魔たちの掛け合いがほっこりする作品です。
『よんでますよ、アザゼルさん。』

ギャグ漫画界の混沌そのもの。
ベルゼブブは賢く、時に可愛く、時にかっこよく、そして……めちゃくちゃ汚い!笑
古い作品ながら、狂気とテンションで、今読み返しても面白い作品です。
まとめ|ベルゼブブの起源を知るとマンガがもっと面白くなる
ベルゼブブは、もともと土着の神がユダヤ教の影響で悪魔へと転じた存在です。
旧約では堕天の仄めかし、新約では悪魔幹部として登場。
中世以降の神学者によって「暴食の悪魔」「サタンの右腕」としてキャラ付けされ、近代文学や現代マンガでも多彩に描かれてきました。
宗教的背景を知ることで、マンガのキャラクター描写やコメディの深みをより楽しめるはずです。






