『呪術廻戦』に登場する伏黒恵。
彼の使う「十種影法術(とくさのかげぼうじゅつ)」は、影を媒介にして式神を呼び出す独特の術式です。
しかしこの“影を操る力”には、ただの呪術を超えた、日本神話との深い共鳴が見え隠れしています。
この記事では、十種影法術に隠された神話的モチーフを手がかりに、
伏黒恵というキャラクターの“影に宿る意味”を探っていきます。
十種影法術の元ネタは「十種神宝」だった?
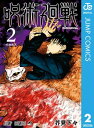
伏黒恵の十種影法術は、影を使って式神を呼び出し、戦闘や守護に利用する術式です。
この十種影法術は、じつは日本神話に登場する十種神宝(とくさのかんだから)がモチーフになっていると考えられます。
十種神宝(とくさのかんだから)とは、太陽神である天照大神の孫、ニギハヤヒが天から地上に降り立つ際に持っていた10の不思議な宝具です。
これらは死者を蘇らせる力や、魂を鎮める力を持つとされています。
- 沈香珠(ちんこうしゅ):死者の魂を呼び戻す香の力
- 藤珠(とうしゅ):精神や感情を整える宝
- 玉祖珠(たまのおやのたま):魂の根源を司る
- 振風玉(ふるかぜのたま):風を起こし、生命の息吹を蘇らせる
- 振雷玉(ふるいかづちのたま):雷を操る。生命の鼓動・覚醒の象徴
- 道返玉(ちがえしのたま):死者の魂をこの世に引き戻す「還魂の玉」
- 鏡・剣など:光・真理・力の象徴
伏黒の「十種影法術」は、この十種神宝に“影(死)”の要素を加えて、死と再生の力として表現されていると考えられます。
影とは「形を持たない領域」。
つまり、魂が肉体を離れたあとの世界を象徴しています。
伏黒はその“影”を自在に操り、そこに「式神=魂の分身」を呼び出す。
言い換えれば、死者の魂を自分の中に再構成して蘇らせている行為でもあります。
「摩虎羅」の呪文と役割
死者の魂を現世に呼び戻すには、「十種神宝を振って呪文を唱えることで死者を蘇らせる」と伝えられています。
ふるへ、ふるへ、死反(まかる)る魂、
生反(いくかへ)る魂、ふるへ、ふるへ。
この呪文、どこか似ていませんか?
摩虎羅(まこら)召喚時の呪文「布瑠部由良由良(ふるべゆらゆら)」に。
この言葉の由来は、日本神話に登場する「布瑠の言(ふるのこと)」という鎮魂の呪詞(じゅし)で、唱えたのは十種神宝の持ち主ニギハヤヒの祖父であり、日本の最初の神様でもあるイザナキです。
イザナキが黄泉(よみ)の国から戻ったあと、
死と穢れを祓うために禊(再生の儀式)を行い、
その時に神々を呼び起こす呪詞として唱えられたのが「布瑠部由良由良」。
つまり──
「布瑠部由良由良」は、“神霊を呼び降ろす(依り憑かせる)ための呪文”なんです。
伏黒が摩虎羅を召喚する時に唱えるこの言葉は、まさに神を降ろす儀式そのものなのです。
時系列で整理すると、次の流れです。
- イザナキが「布瑠部由良由良」と唱えて天照大神が生まれる
- 天照大神の孫・ニギハヤヒが十種神宝を持って地上に降りる
- 十種神宝で魂を蘇らせるときに唱える呪文が
「ふるへ、ふるへ、死反る魂、生反る魂、ふるへ、ふるへ」
つまり伏黒恵は、「死者の世界」と「生者の世界」をつなぐ媒介者であり、十種影法術は黄泉の国から力を引き出す術といえます。
摩虎羅(まこら)との関係:死の循環を司る神
十種影法術の最強式神・摩虎羅(まこら)は、「適応する」存在。
どんな攻撃にも死なず、何度でも蘇ります。
摩虎羅=死を超える再生の象徴。
この“再生”の力を呼び出すとき、伏黒が唱えるのが「布瑠部由良由良」。
摩虎羅はあまりにも強すぎて、伏黒が完全に支配することはできません。
呼び出すことはできても言うことを聞かない。呼び出した者を殺さない限り戻らない。
“死を超える再生”の摩虎羅は死を代償に呼び出すしかない。
摩虎羅は魂の復活の象徴である十種神宝と影(死)を織り交ぜた十種影法術の最終形態と考えられます。
伏黒恵と津美紀の関係性
もし伏黒恵がイザナキをモチーフにしているのなら、姉の津美紀のモチーフはイザナミだと考えられます。
イザナミは火の神を生んで死に、黄泉の国に閉じ込められます。
イザナキは彼女を取り戻そうとして黄泉に赴きますが、その姿を見てしまったことで、地上と黄泉が永遠に分かたれてしまいます。
伏黒恵も、“黄泉のような呪いの世界”に囚われた姉を救おうとします。
イザナミとイザナキの物語はざっくり次のとおりです。
- イザナミは死んで黄泉の国(死者の世界)に行く
- イザナキは彼女を取り戻すために黄泉に向かう
- しかしイザナミの変わり果てた姿を見て、地上と黄泉が永遠に分かたれる
- イザナキは現世に戻り、黄泉の穢れを祓う(禊)ことで神々を生む
つまり、「死者の世界が現世に影響を及ぼす」という構図が生まれます。
伏黒もまた、黄泉(呪い)の世界に繋がる者として、この神話を体現しているのです。
伏黒恵が両面宿儺の器となれる理由
伏黒恵が宿儺の器として選ばれたのは、単なる才能ではなく、彼の術式と神話的背景が深く関係しています。
十種影法術との親和性
伏黒の術である十種影法術は、死者の影を現世に呼び出し操る力。
つまり、「生と死の境界を操る」術です。
死者の力を借り、現世に影響を及ぼす存在である伏黒は、「両面宿儺」にとっては最適な器だったのです。
虎杖悠仁との対比
虎杖悠仁も宿儺の器でしたが、宿儺は完全には支配できませんでした。
それに対し、伏黒は支配された。
この違いは、両者の“性質”にあります。
- 虎杖悠仁 :地蔵菩薩・弥勒菩薩のような「救済と希望」の象徴
- 伏黒恵 :イザナキや十種神宝のような「生と死の循環」の象徴
虎杖は「希望」「救い」の象徴として、宿儺すらも救おうとする。
伏黒は「死の媒介者」として、宿儺の存在を“受け入れて共鳴する”。
その違いが、「宿儺が伏黒を完全に器とできた」理由です。
伏黒恵は「影」と「死」を媒介する存在であり、
神話で黄泉の国を往来したイザナキ、魂を呼び戻す十種神宝、
そして再生を象徴する摩虎羅──それらすべてを内包した“死と再生の器”なのです。
関連記事 -> 『呪術廻戦』考察#1|虎杖悠仁は“現代の菩薩”?依代・地蔵・弥勒が示す隠された意味 (Jujutsu Kaisen Analysis: Yuji Itadori’s Buddhist Motifs)
まとめ:伏黒恵が体現する“死と再生”の神話構造
伏黒恵の「十種影法術」は、単なる戦闘技ではなく、日本神話の「十種神宝」や「イザナミ・イザナキ伝承」を現代的に再構築した呪術といえます。
- 十種神宝 → 魂を呼び戻す神器
- 影法術 → 魂を呼び出す術式
- 摩虎羅 → 死を超えて再生する存在
- 津美紀 → 黄泉に囚われた魂(イザナミ)
- 伏黒恵 → 黄泉へ赴く者(イザナキ)
そして伏黒は、「影」=生と死の境界を自在に操る唯一の術師。
彼が宿儺の器となれたのは、まさに「死と再生を繋ぐ媒介者」だからです。
宿儺との融合は、破壊でも救済でもなく、
“死と生が同居する呪術の完成形”として描かれているのかもしれません。
※※注意※※
この記事で紹介している内容はあくまで考察です。
伏黒恵の十種影法術やモチーフに関する元ネタが明言されているわけではありません。
「こういう見方もあるんだな」と楽しんでいただくことを目的としています。
関連記事 -> 『呪術廻戦』作品紹介|読むほどに深まる戦闘とキャラクターの魅力 (Jujutsu Kaisen: Engaging Battles and Character Appeal)





